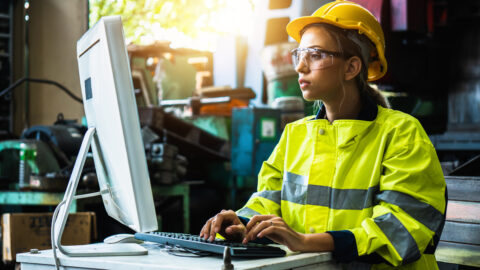おことわり
この記事は、2023年11月にQiitaに投稿した記事を加筆修正したものです。
また、この記事のオリジナルは日本語で書かれています。記事が日本語以外の言語で表示されている場合、それは機械翻訳の結果です。当社は機械翻訳の精度に責任を負いません。
はじめに
DRAMを搭載しないSSD、いわゆる「DRAMレスSSD」が増えました。私たち一般消費者が店頭で購入できる製品では、概ね、高い性能を追求する製品はDRAMを搭載し、コストパフォーマンスを追求する製品はDRAMを搭載しない、のようなすみわけがなされています。
前回の記事では、「DRAMレスSSDを上手く使う方法」として2点説明しました。それは、「大きいサイズで、もしくはシーケンシャルにアクセスする」ことと「空き容量を多くする」です。
今回の記事では、残りの2点を説明します。
まとめ
DRAMレスSSDをより良く使うには、以下のポイントを意識すると良い。
- その3:書き込みを少なくする
- その4:暇な時間(アイドル時間)を作る
その3:書き込みを少なくする
これは「書き込みが少なければGarbage Collection(以下GC)の実行頻度も低くなる」からです。
データを保存することが機能のひとつであるストレージの性格上、ホストからの書き込みがゼロになることはあり得ません。
しかし「一度書き込んだデータを何度も読み出すような使いかた」は存在します。例えば、写真や音楽そして映像などのメディアコンテンツデータを多数保存して何度も読み出して楽しむ、などの使いかたです。このような使いかたであれば、空き容量をきちんと確保しておけばGCの発生頻度を低く抑えることができます。
PCに複数台のSSDを搭載する場合など、使いかたを基準にしてデータの保存先SSDを別々にすることが可能な場合、「記録したデータを書き換えることがあるか?(書き換える頻度が高いか?)」という視点で保存先を決めてかつ使用するSSDを選定すると効果的です。
その4:暇な時間(アイドル時間)を作る
前述の通り、DRAMレスSSDを使う際はできるだけGCを実行しないことが理想ですが、データを蓄積しながら使い続けていく中でGCの実行をゼロにすることは困難です。
そこで「GCの実行に専念する時間を作る」というのがこの方法です。
人間が操作するPCなどの機器であればこのアイドル時間を作りやすいです。休憩のために席を外すだけでも十分な時間を作ることができる場合が多いです。インダストリアル系機器では実稼働時のアクセスパターンを想定することが可能だと思いますので、そのアクセスパターンが十分なアイドル時間を持つかどうか確認すれば良いです。
なお、アイドル時間を有効に活用するにはSSDが「アイドル時にGCを実行する」という機能を持つ必要もあります。しかしアイドル時にGCを実行すると、アイドル状態を脱した直後のコマンド処理に時間がかかる(レイテンシが長くなる)場合があります。また消費電力低減のためにアイドル時に積極的に動作を停止するSSDも存在します。
前者の挙動が起きないようにするため、そして後者を確実に実現するために、「アイドル時にGCを実行する」という機能を持たないまたは無効にしているSSDも存在するので注意が必要です。
おわりに
今回の記事では、「DRAMレスSSDを上手く使う方法」をさらに2点説明しました。
SSDは使いかたに応じて性能や寿命が変わるデバイスですので、DRAMレスSSDの活用には「DRAMレスSSDが適した使いかた」を理解して自分の使いかたがこれに当てはまるかどうかで判断する必要があります。
家庭やオフィスで使用する典型的なパソコン向けのストレージであれば、たいていの場合DRAMレスSSDを活用可能です。逆にそれとは異なる使いかた、例えば24時間365日稼働する機器や過酷な環境で動作する機器、さらには特殊な要件を持つ機器向けのストレージの場合は、DRAMレスSSDの特徴を良く理解して選定する必要があります。
他社商標について
記事中には登録商標マークを明記しておりませんが、記事に掲載されている会社名および製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。
記事内容について
この記事の内容は、発表当時の情報です。予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。